こんにちは、くまのこですよ。
札幌も6月から30度超えの日が続き、北海道民は暑さで虫の息です。
かくいう私も身体が灼熱の大阪仕様から北海道仕様にチェンジしてしまっているので
めっちゃ弱ってます!!!
さて、近頃は2025年7月になんちゃらな予言とかでざわつきましたね。
北海道でも5月、6月と地震が続いたこともあって不安な気持ちがムクムクと膨らんでいます。
ということで今回は移住者目線で考える北海道での防災対策についてまとめていきます!
北海道で想定される自然災害とは?
「北海道は災害が少ないから安心」と言われることもありますが、実は全然油断できません!!!
移住して初めてわかる、北海道ならではの自然災害リスクを知っておきましょう。
地震
2018年9月、北海道胆振東部地震が発生。最大震度7を観測し、全道で大規模なブラックアウト(全域停電)となりました。
私はまだ移住する前だったのでこのブラックアウトは経験していませんが、もし真冬に慣れない北海道で停電が起こったら?と想像するだけでもゾっとします。
地震は北海道でも発生します。特に札幌市内でも清田区などは地盤が弱いとされ、液状化現象が話題になったこともあります。
自分が住む予定の地域のハザードマップは必ずチェックしましょう。
大雪・猛吹雪
北海道の冬といえば雪。
ですが、観光のきらきら雪景色☆なイメージとは裏腹に、大雪やホワイトアウト(視界ゼロの吹雪)は日常生活に大きな影響を与えます。
・交通機関が丸一日止まる
・車が雪に埋もれて動かせない
・買い物に行けない日がある
移住者として最初に驚くのは、これが「想定内の冬の暮らし」だということ。
除雪体制が整っている札幌でも、天候次第では外に出られない日があることを前提に、食料や暖房の備えが必要です。
土砂災害や洪水
札幌市内にも山が近い地域や川沿いの住宅地があります。大雨が降った際には、土砂崩れや河川の氾濫リスクがゼロではありません。実際、過去には札幌の南区や清田区などで土砂災害警戒区域が指定されたことも。
都市型災害とは違う「自然との距離の近さ」が、北海道の住環境の特徴です。
蝦夷梅雨・台風の影響は?
北海道は梅雨がないと言われますが、6〜7月にかけて「蝦夷梅雨」と呼ばれるぐずついた天気が続くこともあります。
また、本州で発生した台風が勢力を弱めながら北上することも。
「北海道は台風の心配が少ない」と言っても、強風や雨で倒木や停電が起こる可能性もあり、過去には被害が出たこともあります。
特に一軒家に住む場合は、風への備えも意識しておくと安心です。
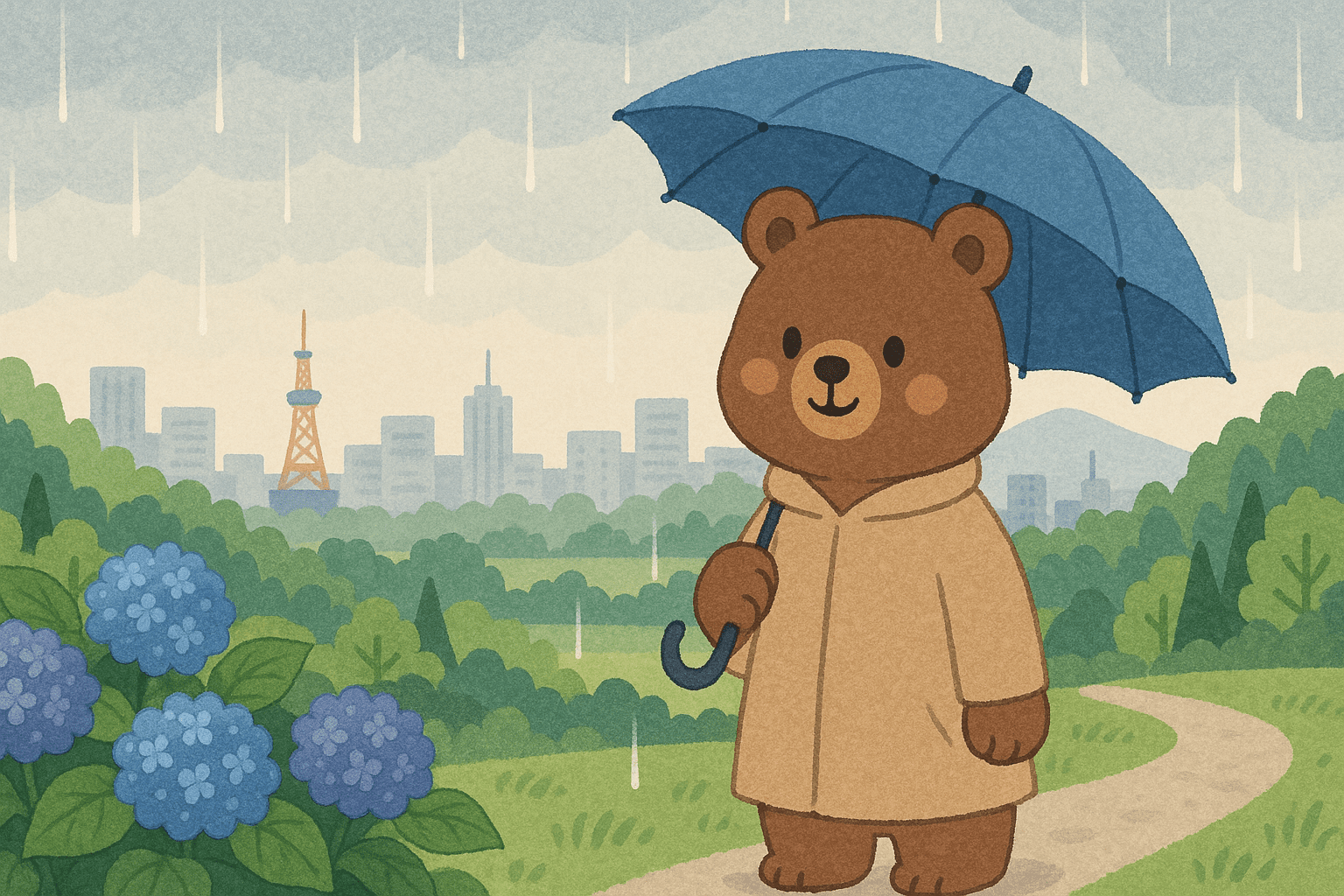
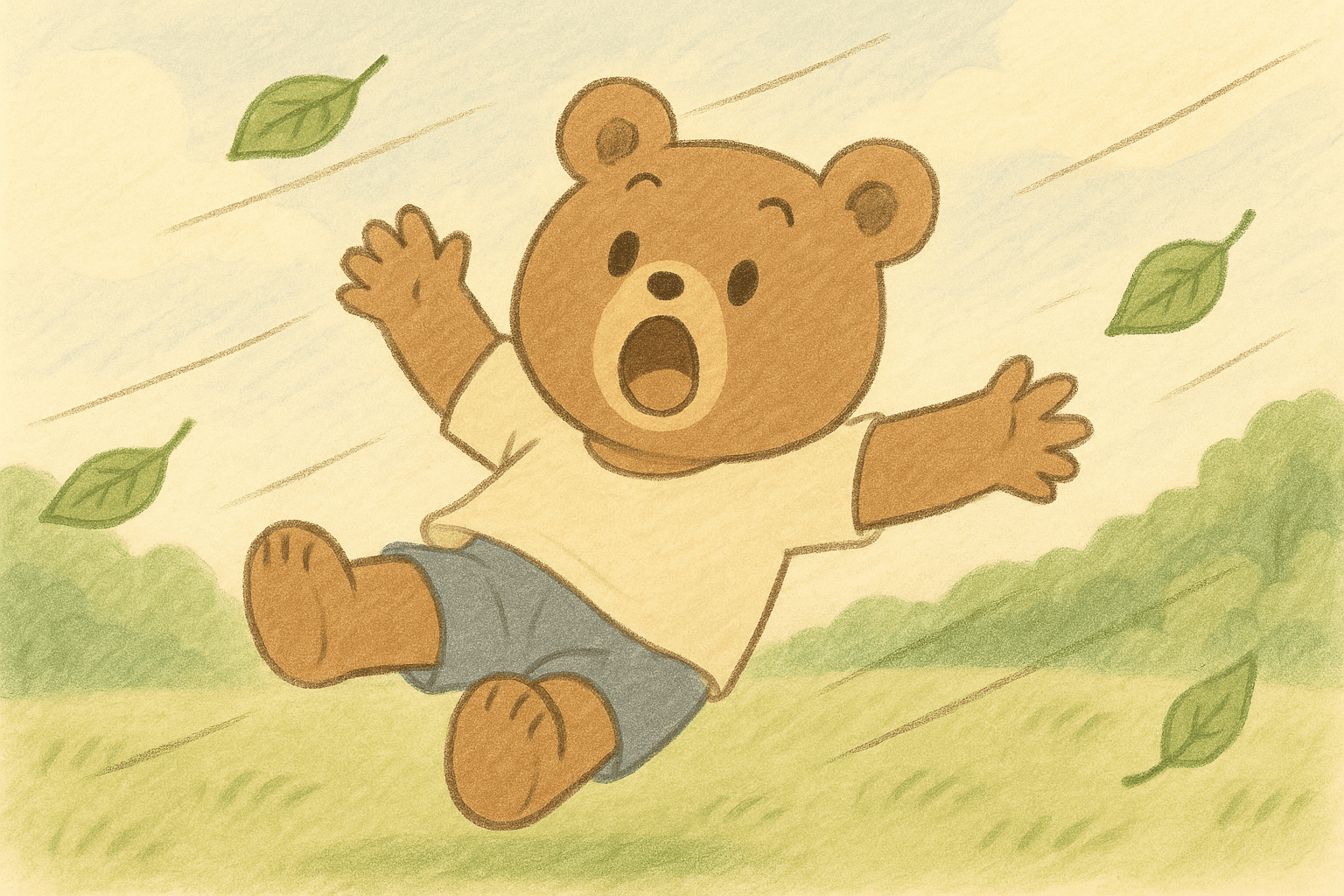
本州とココが違う!北海道の災害リスク
北海道に移住して実感したのは、「災害が起きたときに直面する現実」が本州とはまったく違うということ。地震・停電・雪という条件が重なったとき、備え方や生活の工夫には雪国ならではの対策が必要です。
停電リスクと冬の寒さのダブルパンチ
北海道の冬に停電が起きたらどうなると思います?想像しただけでヤバくないですか?
本州では停電=不便、ですが、北海道では停電=「命に関わる」可能性があります。理由は暖房。冬の北海道は氷点下が当たり前。電気で動く暖房機器が止まると、室内が一気に冷え込み、家の中でも凍えるような寒さになります。
厳冬期なら水道管はもちろん凍結してしまうし、下手すると備蓄してる水も凍るでしょうね。
2018年の胆振東部地震では、9月にもかかわらず「夜は寒くて眠れなかった」という声も多く聞かれました。これが1月や2月だったら…と考えると、停電への備えは必須です。
暖房設備が命綱!「電気 vs 灯油」の選び方
本州ではオール電化住宅やエアコン暖房が一般的ですが、北海道では「灯油ストーブ」がまだまだ主流。特に「FF式ストーブ(強制給排気式)」は、外気を使って燃焼し、室内の空気を汚さずにしっかり暖まる優れものです。
ただし、FF式も電気がないと動きません。そこで活躍するのが「電源不要のポータブル石油ストーブ」。移住後に1台持っておくと、いざというときの安心感が違います。
灯油の備蓄については、ホームタンクがない場合「ポリタンク×数本+灯油ポンプ」で自分で備える必要があります。我が家もそうですが、賃貸マンションなどは石油ストーブ使用不可の物件が多数存在します。そんな物件に住む人が用意するべきはこれ。カセットガスストーブ。もちろん電源も不要です。
これならストーブの上に鍋ややかんを置いて湯沸かしや保温ができます。この機能は災害時に大きなメリット。燃焼器具なので1時間に一回は必ず喚起をしてくださいね。あと可燃物は近くに置かないように。
ストーブの熱は上に上がりますので、ストーブファンを上に乗せればファンヒーターにも早変わり。電源不要です。
北海道ではカセットガスは多めに備蓄しておくのが安心です。使用期限は約7年ですので適度に鍋などをしながらローリングストックしていくといいですね。
下記に岩谷さんのサイトのカセットガスの試算明細表を貼っておきます。
備蓄食料の内容、カセットこんろの使い方等を、ご自身の場合にあてはめて試算の参考としてください。
想定用途分(2人分) 沸かす水量 使用鍋 気温 沸き上げ+維持時間 消費ガス量 1日3回の必要ガス消費 1日当たりの必要本数 食事 レトルト惣菜
パックご飯(各2個)1ℓ 20cm
両手鍋25℃ 強火4分30秒+
中火15分強火17.7g+
中火29.5g47.2g×3回=141.6g 0.6本 10℃ 強火7分40秒+
中火15分強火30.2g+
中火29.5g59.7g×3回=179.1g 0.7本 カップ麺(大)2個 1.2ℓ やかん 25℃ 強火5分 中火19.7g 19.7g×3回=59.1g 0.2本 10℃ 強火8分 中火31.5g 31.5g×3回=94.5g 0.4本 飲み物 温かい飲み物
(250ccを2杯)0.5ℓ やかん 25℃ 強火2分30秒 9.8g 9.8g×3回=29.4g 0.1本 10℃ 強火4分 15.7g 15.7g×3回=47.1g 0.2本 お湯 お湯を沸かす
(洗浄、殺菌等)1.2ℓ やかん 25℃ 強火5分 19.7g 19.7g×3回=59.1g 0.2本 10℃ 強火8分 31.5g 31.5g×3回=94.5g 0.4本 実験条件:カセットこんろは発熱量2800kcal/hのもの。
鍋は薄手のアルミ鍋(フタなし)、やかんはステンレス製のものを使用し、無風状態で実験。※上記は備蓄の参考、目安です。イワタニカセットガス1本には250g入っています
ご紹介したはカセットガスストーブでは火力が足りないため、調理はできませんのでカセットコンロも1台用意しましょう。非常時でなくとも寒い北海道の冬はお鍋がはかどりますよ。キャンプやBBQにガンガン使いたい人は下の風まるよりさらに風に強いタフまるがいいかも。
移住者が知っておきたい北海道の防災対策の基本
防災グッズは「冬仕様」が最重要
防災リュックや備蓄品といえば、食料や水を思い浮かべがちですが、北海道では「寒さをしのぐ工夫」が非常に重要です。
✔ 毛布・寝袋(冬用)
✔ カイロ(使い捨て/繰り返し使えるタイプ)
✔ 手回し式や電池式のLEDランタン
✔ 結露しない断熱シート(窓や床に貼ると保温効果UP)
また、バッテリーやスマホの充電器も、寒さで性能が落ちやすいため、複数の電源手段(モバイルバッテリー・ソーラー・乾電池式など)を持つのが安心です。
近所の避難所とハザードマップを必ず事前にチェック!
移住後、災害が起きてから避難所を調べる…では遅いです!!札幌市では各区ごとに避難所が設定されており、ハザードマップも公式サイトで公開されています。
✔ 自宅や職場から一番近い避難所はどこか
✔ 地震・土砂災害・洪水などのリスクはあるか
✔ 避難所の設備(暖房・トイレ・収容人数)
こういった情報は引っ越し前後に一度チェックしておくと、いざというときに慌てずに行動できます。同居の家族とも緊急時はどう行動するかの話し合いも必ずしてください。移住先に住み慣れるまでの土地勘がない時期はとくにしっかりと決めておくことが重要です。
実体験で語る!私の防災準備
移住候補地のハザードマップは必ずチェックする
移住先を選ぶ時点で絶対にハザードマップは確認した方がいいです。どれだけ理想の場所だとしても調べると災害に弱いエリアだったということがたくさんあります。
私の場合はかなりの心配性のため、住んでみたいなと思ったエリアのハザードマップはくまなくチェックしました。災害は地震や大雪だけではありません。地震で揺れやすい地盤や液状化のしやすさだけではなく、川の氾濫や土砂崩れ、海の近くなら津波もあるでしょう。
北海道でも近々大きな地震が起こりえます。津波が想定されている地域もあります。気候変動によって台風が毎年上陸するような事態も想像に難しくありません。
どこに住むとしても備えは絶対に必要ですが、できるだけ後悔のない移住ライフを送るためにも見ておきましょう、ハザードマップ。
全国どこでも検索できるくまのこイチオシのサイト
札幌市では札幌市地図情報サービスが見やすくて便利
冬の災害を想定したわが家の備蓄
- 食料
-
いわずもがな、簡単に調理できる麺類やパックごはん、レトルト食品、カロリーメイトのような手軽にカロリーをとれる補助食品等。非常食界のレジェンド「乾パン」も常備。被災時に心を癒す羊羹や飴なども常備。
- 水
-
飲料水の他にも生活用水として空いたペットボトルに水道水を入れて数本を冷蔵庫に常備。
- クーラーボックスや寝袋
-
クーラーボックスはキャンプ道具としても使えるし、停電で冷蔵庫が使えなくなった場合にとりあえず冷蔵、冷凍のものを非難させることができる。寝袋は冬でも使えるものを用意。子どもがいるので親子で入れるものを購入。密着すればあたたかいし不安な気持ちも和らぎそうと思っている。
というかこの際キャンプも始めちゃいましょう!おのずと防災道具が揃います。
- ホッカイロやガスストーブなど防寒グッズ
-
北海道は本当に寒さで人が亡くなるのでこれだけは絶対に必要。その他にもスノーウエアやグローブ、ニット帽もいつでも取り出せるようにしている。
- 非常持ち出し袋と持ち歩き用防災ボトル
-
ライトやラジオ、軍手、ラップ、衛生用品、バッテリー、水、ウェットシート、テープなど。
持ち歩きボトルには100均で購入した、笛や飴、水で戻すタオル、ばんそうこう、ライト、現金、連絡先を書いた紙などを入れて普段のバッグに入れて持ち歩いています。
まとめ|移住してからでは遅い!備えは暮らしの安心につながる
「北海道は災害が少ないから大丈夫」——そう思って移住してくる方は少なくないです。もちろん私もそのひとりでした。しかし実際に暮らしてみると、地震・停電・大雪といった自然の脅威に、“寒さ”という独特の環境要素が加わることで、本州とはまた違う備えが必要だと気づかされました。
特に冬の災害では、暖房やライフラインが止まることによって命に関わることもあります。だからこそ、「もしも」に備えることは不安を減らし、安心して暮らすための土台になります。
私自身も、道外から移住して初めて知ったこと・感じたことが本当にたくさんありました。
だからこそ、移住を考えている人たちに向けて、リアルな経験をシェアすることが誰かの安心につながると信じてこれからも発信していきたいと思います。
災害対策は一度で完璧にできるものではありません。少しずつでいいので、「冬の北海道で安心して暮らすための準備」を始めてみてくださいね。
最後までお読みいただきありがとうございました。
